「このままSEとしてキャリアを終えてもよいのだろうか」、「最近あまり成長できていない気がする」
SEとしてのキャリアは非常に魅力的で、様々なプロジェクトを経験できる職業です。しかし、30歳を過ぎると、次第に自分のキャリアパスに関して悩む時期が訪れます。それは「このままジェネラリストとしてマネジメントに進むべきか、それともスペシャリストとして特定の分野で深堀りすべきか」といった悩みです。
この記事では、私自身も同じ悩みを抱えていた理由と、それに対してどのように決断したのかをお伝えしたいと思います。SEとしてのキャリアに悩んでいる方への、今後の方向性を見つける参考になれば幸いです。
※ちなみに、私がSEこそITコンサルに転職すべきと考える理由は以下に記載しています。
【結論】スペシャリストになるべきと感じた
私は30歳を過ぎたあたりから、常々、ジェネラリストとしてマネジメントを行うだけでは、自分の存在価値があるのか?と疑問を感じていました。SEとして、プロジェクトに関わりながらも、実際には下請けベンダーに多くの仕事を委託し、マネジメントや調整に回ることが多くなります。
この中で、技術的なスキルが伸びなく、顧客との本質的な議論の機会が少なく、このままあと30年以上もこの働き方でよいのだろうかと感じるようになったのです。そこで、ITコンサルに転職する道を選びました。
ジェネラリストだと存在価値を感じにくい
実際に顧客と要件定義や設計の結果をレビューしてもらうのは、下請けベンダーの役割で、SEとしての自分はその場でファシリテーションをするだけです。業務フローのような資料を作るのはSEではありません。
確かにファシリテーションも重要な役割ですが、それであればITコンサルのような会社の方がスキルが身につくと感じました。実際、同じプロジェクトにコンサルティングファームのメンバも入っていて、その人たちの方がよりマネジメントのスキルに特化していたと感じました。
存在価値を感じられない事例
例えば、以下のような場面で存在価値が感じられませんでした。
要件定義等の上流工程でも下請けベンダーが顧客と議論
SE時代は、要件定義や設計などの上流工程からのプロジェクトに参画したとしても、実際に顧客との打ち合わせや業務フローの説明などは、ほとんどが下請けベンダーにて実施していました。というのも、やはり具体的な業務は下請けベンダーの方が詳しく、SEはファシリテーターとして議論を進めるだけであり、本質的な議論に関わることが少なくなっていきました。
このように、実際に顧客と議論する場面が減っていくと、自分の存在価値を感じにくくなります。ファシリテーションの役割も重要ですが、「この場にいる意味はあるのか」と、顧客からの信頼を得られていないと感じることがありました。
そもそも、SEができるものも下請けベンダーに流すビジネスモデル
SEの仕事の中で、「できるけどやらない」ということが多いと感じました。自分たちでも要件定義を行い、設計できるプロジェクトもあるのですが、それを下請けベンダーに任せることで利益率を上げるビジネスモデルになっているため、実際に手を動かすことが少なくなります。
このため、SEとしての専門性を深める機会が減り、どんどんジェネラリストとして広い範囲での調整役に徹するようになります。SE自身が手を動かす機会はほとんど無く、スペシャリストとしての成長は無いんだなと感じ、存在価値を感じにくいと思うようになりました。
それでも、SEが進捗報告
要件定義や設計等の本質的な部分を進めるのは下請けベンダーになりますが、顧客への進捗報告はSEがやらなければなりません。状況を把握できていても、実際に進めていないので、他人がやったことを報告するということで、あまり存在価値を感じることができませんでした。
詳細な質問が来たりすると、下請けベンダーに回答をお願いすることになり、そういった場面があったことからも、自分自身がスペシャリストになりたいと思うようになりました。
まとめ
ITコンサルに転職して感じたことは、やはりスペシャリストとしてのスキルを深堀りする方が、自己実現やキャリアの満足度が高いということです。SEとしては、ジェネラリストとしてプロジェクト全体を管理する役割が増えますが、その分、自分の専門性が薄れていく感覚があります。こういった私の考えが、今後のキャリアの参考になれば幸いです。
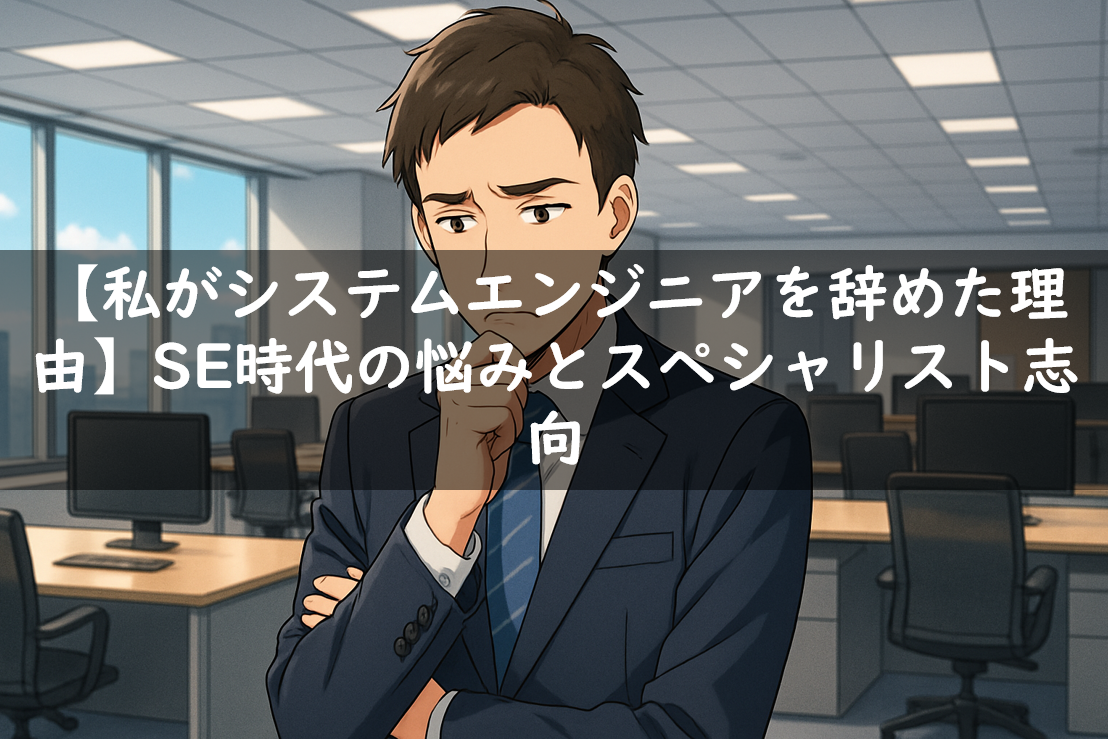
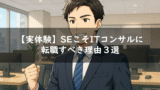

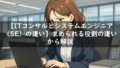
コメント