「ITコンサルって何をしている仕事なのかわからない」
「SEがコンサルに転職できるのか」
「ITコンサルに転職している人って前職でどういう仕事していたんだろう」
「具体的にどういう仕事内容がITコンサルに活かせるのかな」
ITコンサルへの転職に興味があるSEの方は多いのではないでしょうか。もっと上流からプロジェクトに携わりたい、IT以外の面でも顧客と接したい、年収を上げたい・・・といった内容がSEがITコンサルに興味を持つ理由かと思います。
ただ、ITコンサルのイメージから、深夜まで仕事をしていて激務そうであったり、みんなスキルが高いからそもそも自分にできるのか、といった不安があると思います。
そんななかなか一歩を踏み出せない方に伝えたいのが、SEこそITコンサルに転職すべきということです。
私自身、日系大手SIerでSEとして8年働いた後、外資系総合コンサルファームへ転職しました。転職して年収は1.5倍になりましたが、業務量はほとんど変わりませんでした。
とはいえ、ITコンサルに転職した後に苦労する点もあるので、その点も注意点として考慮していただき、その点も踏まえて、ITコンサルが自分に合っていそうかを検討してもらえればと思います。
本記事では、SEはITコンサルに転職する理由を、実体験をベースに紹介します。「ITコンサルに転職できるか不安」「そもそもITコンサルって何をしているのか」という方への転職の参考になれば幸いです。
ちなみに、私がSEからITコンサルに転職した理由を以下の記事にまとめていますので、もし興味があれば覗いてみてください。
SEこそITコンサルに転職すべき
まず、SEの方にとって、ITコンサルは近い存在だと思います。SEとITコンサルが同じシステム導入プロジェクトで一緒に働くことがよくあります。役割の違いがあるものの、システムを導入するという同じ目的に立って仕事をしているという点で共通点があります。
私自身、SE時代に要件定義準備などの上流工程からプロジェクトに参画していたとき、SEとITコンサルの仕事内容の何が違うのか分かりませんでした。実際、コンサルに転職してみると、やっていることはSEと似ているのに、待遇はコンサルの方が明らかに良いと感じました。
仕事内容は似ていて、年収が高いとなると、一度転職を検討してもよいかなということが伝わったかと思います。ただもちろん、ITコンサルに転職するうえで注意した方が良いと思う点を私なりの考えもお伝えしたいと思っています。
次から、転職すべき理由と注意点を具体的にお伝えします。
転職すべき理由3選
私が実際に転職活動をしてみて、SEこそITコンサルに転職すべきと思った理由をお伝えします。当時はあまりコンサルのことはあまりわかっておらず、同じプロジェクトにコンサルの人がいるので転職先の候補の一つくらいでした。コンサルの仕事の話を聞いていくうちに、SEこそコンサルで働くべきだ!と思いましたので、その理由をお伝えします。
SEでの現場経験が強みになるから
私がITコンサルに転職した際に実感したのは、SE時代に培ったチームリーダーとしての経験や現場メンバと一緒に働いた経験がそのままITコンサルとしての仕事に活かせたということです。
コンサルでは、IT関連やシステム導入のプロジェクトからは離れてしまうのではないかと思っている方も多いのかなと思いますが実際は違います。コンサルティングファームに転職しても、システム導入のプロジェクトは想像以上に多く大半を占めています。
特にSAPなどのERP関連案件では、ITコンサルが携わることが多いです。これは私がITコンサルに転職して驚いたうちの一つになります。要件定義~稼働まで、SE時代と同じ領域を担当することが何度もありました。実際にSEとしてシステム開発に携わった経験は、コンサルに転職すると貴重な価値になります。
SEとITコンサルは同じ仕事内容だから
ITコンサルとして働いている中で、SE時代のことを振り返ると、SEの時からコンサルと同じような仕事をしていました。先ほどお伝えした通り、ITコンサルでも、システム導入のプロジェクトが多いためです。
ITコンサルはPMOを担当することが多いため、まさに同じ仕事内容をSEとITコンサルでも実施することになります。プロジェクト全体を見渡して、課題管理や進捗管理、またスケジュール調整等のプロジェクトが円滑に進むための役割はSEでもITコンサルでも実施することになります。
また、SE時代から、要件定義準備というような要件定義開始前からプロジェクトに参画し、顧客と直接会話しながらニーズを引き出したり、稼働までのスケジュールを立てていました。要件定義より前からプロジェクトに参画し、プロジェクト発足の背景を理解したうえで、顧客と要件定義を開始していく流れはまさにコンサルの仕事と重なる部分です。
それでも、年収が大きく違うから
何より驚いたのは、仕事内容が大きく変わらないのに、年収が1.5倍になったことです。私の場合、転職前は年収700万円程度でしたが、それが転職後には1100万円を超えました。もちろんすべてのコンサルティングファームがそうとは限らないとは思います。
SEの仕事内容と全く同じではないのですが、ここまでお伝えしてきたように、SEでの経験やスキルを活かすことができ、そのうえで年収が大きく変わるというのがITコンサルという仕事だと感じました。
それほど仕事内容が変わらないのであれば、年収が高い方が良いというのは一般的な感覚だと思います。しかし、転職後に感じた注意点もありますので、これからお伝えしたいと思います。

ITコンサルに活きたSE経験の具体例
ここからは、実際に私が経験した具体的なプロジェクトを例に、どのようなSEの経験がITコンサルの仕事に活かされたかを紹介します。
倉庫管理システム導入プロジェクトのチームリーダ
最初に紹介するのは、倉庫管理システム導入プロジェクトでの経験です。私が担当したのは、倉庫管理システムのチームリーダーとして、顧客との調整やチームの管理レビューを行う役割でした。
顧客側現場メンバーとの打合せ調整
プロジェクトの進行中、顧客の現場メンバーが忙しく、打合せの時間を十分に確保できないという課題がありました。この問題を解決するために、顧客と進め方を相談し、打合せの事前に資料を送付して、顧客に論点を洗い出しておくという方法を取りました。
このように現場のメンバが忙しいという問題はつきもので、顧客と臨機応変に対応を調整するというのは、ITコンサルになっても必要な考えです。そういった現場レベルで起きそうな問題をSE時代に肌感としてわかっていたのはとても強みになったと考えています。
チームの管理、レビュー
ベンダーの進捗管理や課題管理をしたり、作成物のレビューをした経験は、ITコンサルに転職後も大いに役立ちました。SE側は実際にどのように作業を進めるのかを知っていることは、ITコンサルとしてSE側とコミュニケーションをとるうえでとても重要です。
というのも、SE側とコミュニケーションをとり、遅延や課題を早期に発見したり、具体的にどんな作成物を作っているのかを理解することは、ITコンサルに求められる期待値であり、プロジェクト管理において大切なスキルになるからです。
基幹システム導入プロジェクトのPMO
次に紹介するのは、基幹システム導入プロジェクトでのPMO業務です。このプロジェクトでは、SAPモジュールの課題管理、進捗管理を担当し、顧客との打合せ調整も行いました。
課題管理、進捗管理
PMOとして、課題管理や進捗管理を行いました。このプロジェクトでは、モジュールごとにチームが組成されていたので、各モジュールから課題をあげてもらったり、進捗を報告してもらっていました。
その中でチーム横断的に検討が必要な課題が出てくるので、そのチーム間の橋渡しをしたり、進捗の評価をしていました。
顧客との打合せ調整
PMOとして、プロジェクト全体を考慮して打合せの優先順位を見極め、顧客と調整するという経験をしました。スケジュール上、いつまでに決まっていないといけないので、打合せをいつまでに実施したいという交渉はITコンサルとしても必要なスキルになります。
意外と、顧客からリスケされて、内部の調整をが必要になったりと、打合せ調整は一見簡単なように聞こえますが、難しく重要なタスクになります。
転職後に感じた注意点
私は実際にSIerから外資系総合コンサルファームに転職し、転職してよかったと思っているのですが、一方で、転職後に「これは想定外だった」と感じた点もありました。
大前提として、コンサルは単価が高いため、顧客からの期待値が高く、それに見合う成果が求められます。そのため、内部レビューがSEの時より圧倒的にハードルが上がっています。
その点を踏まえて注意点を紹介します。
コアコンが不足しがち
コアコン(=コアとなるコンサルのスキル)が圧倒的に不足しているという点です。
「元SEだとロジカルシンキングが足りないことが多いんだよね」
「まだ事業会社にいたころの考え方が抜けていないね」
というような感じで、資料作成の時にコンサルとしてのスキルが不足していることを指摘されていました。
最初はそのギャップに驚かされました。コンサルとして資料作成や提案を行う際に顧客への論理的に説明する能力は、SE時代には意識できていなかったのだと痛感しました。
他のIT系のスキルはSEでの経験から問題ないと感じたのですが、コンサルとして必要なロジカルシンキングのスキルは、SEの時の課題解決力や提案力よりもさらに高いレベルで求められます。
コンサルの一丁目一番地といえば、ロジカルシンキングなため、コアコンスキルが備わっていないと、上司との資料レビューの場でかなり詰められます。私自身、何度もメンタルを削られそうになりましたが、そのプロセスを通して、ロジカルシンキングや資料作成のスキルは確実に伸びたと感じています。
SEにコアコンのスキルが不足するのは、ITコンサルと求められる役割が大きく異なるからだと考えています。SEは主にシステムを開発するための下請けベンダーの管理やITの技術的な観点での議論を顧客と行います。
プロジェクトの進行管理や技術面でのリーダーシップが求められることはあっても、情報を整理し、論理的に他者に説明するという役割はITコンサルに比べると少ないです。
元SEが資料レビューで詰められる理由
ここからはなぜ元SEだとコアコンが不足するかを私なりの考えをお伝えしたいと思います。
パワーポイントで資料作成する機会があまりない
SE時代は、パワーポイントで資料を作成することがITコンサルに比べると少なかったと感じます。ITコンサルは、パワーポイントで顧客に向けた提案資料や報告資料を作成する機会が非常に多く、その都度、論理的な構造やストーリー作りを意識しなければならないため、嫌でも鍛えられました。
SEはパワーポイント資料を作ったとしても、あまりロジカルな資料になっているかといった観点でのレビューがコンサルと比べて少なかったと思います。
エクセル資料の作成機会が多い
SE時代は、エクセルでWBS作成や課題一覧等をする方がパワーポイント資料より多かったと思います。細かいタスク管理等はエクセルの方が使いやすく、そういった細かい管理が多かったため、エクセルを駆使していました。
このスキルはITコンサルに転職後も非常に役立っていますが、エクセル資料はどちらかというと情報を整理し、管理するためのツールに過ぎません。
コンサルは、発生した課題から原因やその打ち手を検討し、顧客に伝えるスキルが求められます。つまり、エクセルの資料はどんなに整理されていても、必ずしも相手に納得してもらえるとは限らないということです。
強いて言うなら提案書は作っていたが、指摘のレベルが低い
SE時代は、提案書や報告書を作成することはありましたが、構造化されていないことや論点の解像度が粗いことへの指摘はありませんでした。論点をもっとシャープにしないと議論が発散してしまうといったレビューをされた記憶がないです。
おそらく、SEにはそういう指摘ができる能力のある人が少ないのだと思います。
ITコンサルは、説明資料で顧客にどれだけ納得してもらえるかが重要です。そのためには、資料が分かりやすいかが問われます。上司からも、資料の論点が曖昧だったり、構造化されていないと厳しく指摘されることが多く、最初はその指摘のレベルに驚きました。
おすすめの1冊
もしこれからITコンサルを目指すなら、以下の本を読んでみるのがおすすめです。面白くてわかりやすく、誇張されているように見える部分もありますが、意外と実態に近い内容で、転職前に読んでおくと、イメージが付くと思います。
他の本の似ている本もいくつか読んだのですが、この本だけ読めば大丈夫です。
まとめ:SEの経験は、そのまま武器になる
SEこそ、ITコンサルに転職すべきです。理由はシンプルで、似たような業務内容で、より高い報酬と裁量を得られるからです。自分はまだ早いかもと思っている方にこそ、まずは情報収集を始めてみてほしいです。この記事が今後のキャリア選択の参考になれば幸いです。
転職エージェントを活用することで、手軽に効率よく情報収集をすることができます。今の自分にはどんな求人があるのかなという興味本位でよいと思いますので、まずは登録だけでもしてみることをお勧めします。
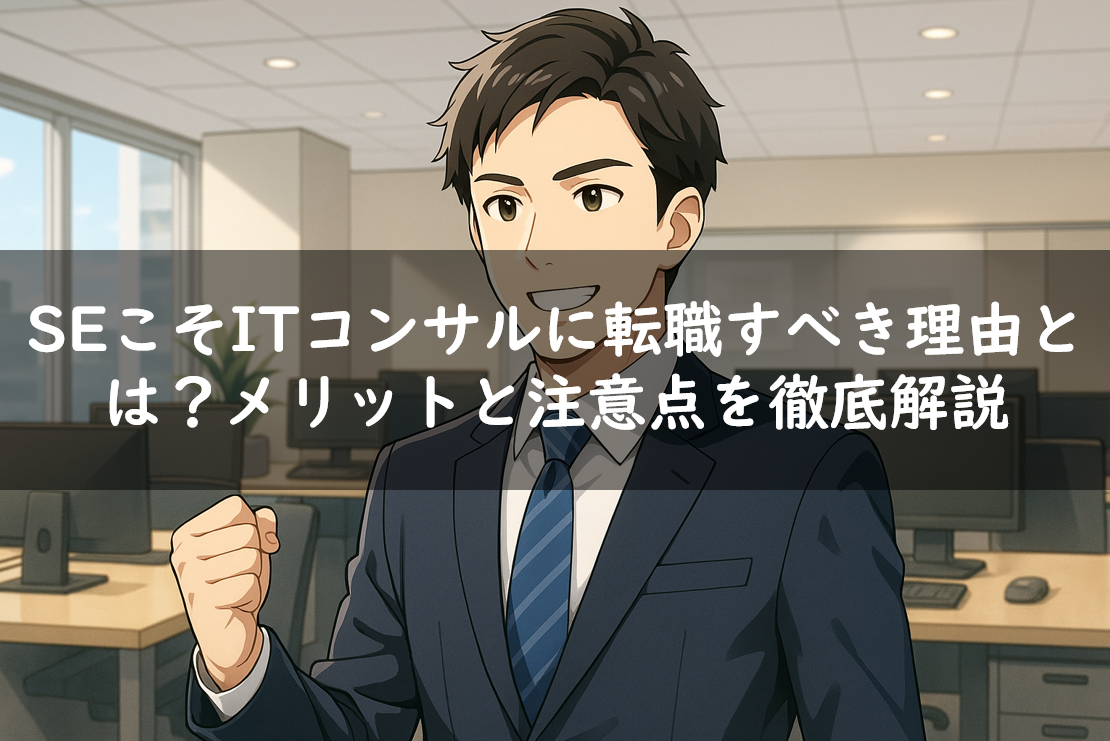
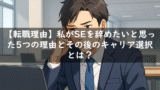
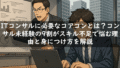
コメント