「SEからITコンサルに転職したいけどやっぱりSEの方がよかったって思うことはないのかなあ」、「一般的にはSEからITコンサルへの転職はあるけど、ITコンサルからSEへの転職ってないのかなあ」
ITコンサルとSEはシステム導入に携わるという面では同じなのですが、実際にシステムを設計し、構築するSEの役割と、戦略や企画の立案を主に行うITコンサルの役割といった違いがあります。私自身もSEからITコンサルに転職した際、その違いを実感しました。
この記事では、ITコンサルに転職して気づいたSEの方が自分に合っている部分があると思った理由について、具体的な事例を交えながら解説します。SEは顧客の要件を具体的なシステムに落とし込んでいく部分でITコンサルと違うのがポイントです。もし、ITコンサルとSEの違いについて悩んでいる方がいれば、この記事を読んでキャリア選択の参考になれば幸いです。
ちなみに、私は総じてITコンサルに転職してよかったと思っていて、その理由は以下に記載していますので、もし興味があれば覗いてみてください。
【結論】SEはシステムという形まで見届ける
ITコンサルの仕事は、良くも悪くも上流工程の企画や戦略を立てることが中心です。しかし、実際に顧客の要件を具体的な形にできるのはSEの仕事です。
SEは上流から下流の工程まで幅広く関与するため、工程の途中で顧客が抱える問題やニーズをシステムに反映させ、最終的な形になるまでを見届けることができます。この過程には、顧客の特に業務部門と直接的にコミュニケーションを取りながら進める部分が多く、非常にやりがいがあります。
コンサルは良くも悪くも形になる前の上流工程が主戦場
ITコンサルの役割は、顧客の課題を抽出し、それに対する解決策を提案することです。しかし、その提案が実際にどのようにシステムとして実現されるのか、その部分を担当するのはSEになります。例えば、ITコンサルは、企業の業務プロセスの改善案を検討しますが、そのプロセスに沿ったシステム開発や導入作業はSEが実施します。
そのため、顧客の要件が形になる過程には深く関与することができず、SEが要件定義から設計、開発、テスト、そして最終的なシステムの導入に至るまで、一貫して関与できるため、成果が目に見える形で現れることに大きな満足感を得られます。
SEが自分に合うと感じた場面
顧客の要件を最終的な形にできる
SEの時、顧客からの要件を実装することを行っていました。顧客が抱える課題をヒアリングして、システム要件に落とし込み、システム化されたものを顧客に提案する作業を行っていました。システムがどんどん形になっていくのを目の前で見ることができ、顧客と一緒に検討したものが最終系としてシステムという形になることに非常にやりがいを感じていました。
実際のシステムで説明できるため顧客に納得感がある
ITコンサルは、まだ上流工程のため、顧客への説明が、パワーポイントの紙芝居かできてもモックアップとなってしまい、顧客が腹落ちしないまま検討が進んでしまうことが多いです。一方、SEは、システム開発の途中段階で、顧客に実際のシステムで説明できます。
これにより、顧客がシステムの仕様について不明点を質問した際に、実際にシステムを操作しながら答えることができるため、顧客に納得感を与えることができます。この実際のシステムを通じた説明は、ITコンサルタントではできない部分であり、SEとしての仕事の魅力だと感じました。
自分も手触り感がある
ITコンサルが活躍するシーンは、まだモノがない工程のため、どうしても「手触り感」が薄くなります。一方SEは、システムを設計し、開発して、テストを行い、実際に顧客の環境で動作させるという一連のプロセスを経て、システムが実際に動く様子を目の前で見届けることができます。
この「手触り感」がSEにはあり、私はその実感が非常に大きなやりがいだと感じました。自分の手で作り上げたシステムが動くのを見た時の充実感は、ITコンサルタントとしての仕事では味わえなかった部分です。
まとめ
ITコンサルに転職してみて、SEの方が自分に合うと感じる場面がある理由は、具体の形にできることでした。ITコンサルとして上流工程での企画や戦略立案に携わるか、SEとして顧客と密に連携しながらシステムを作り上げるか、この観点も大切だということが伝われば幸いです。
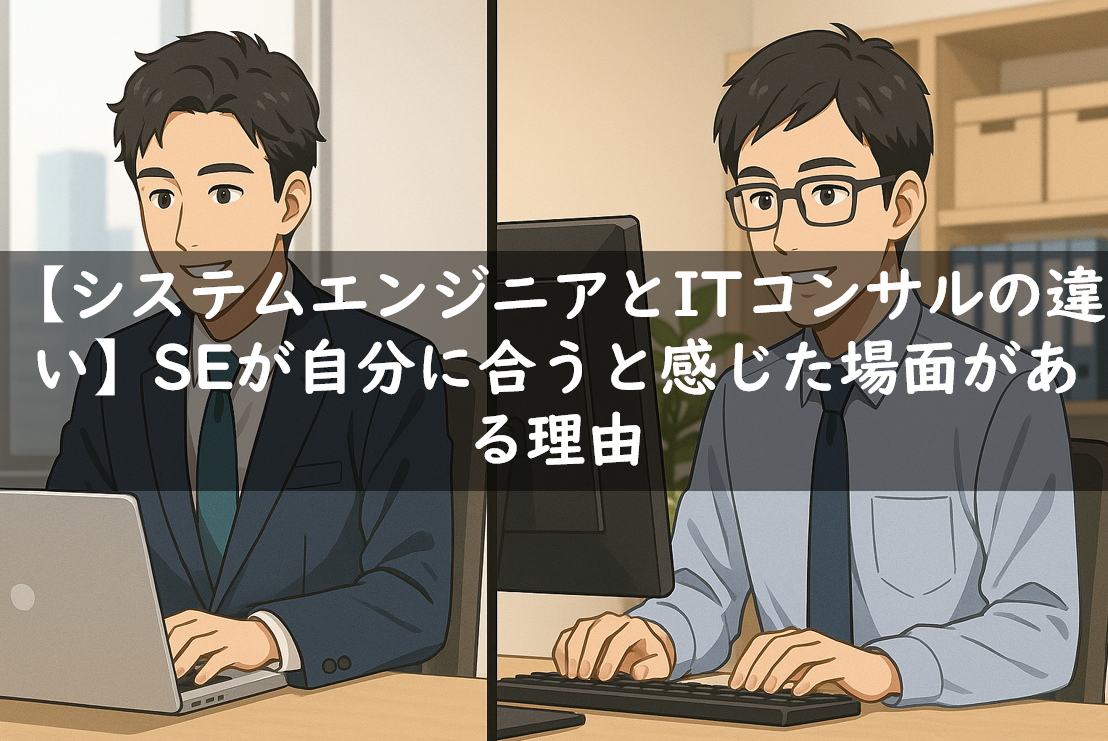
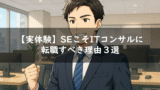

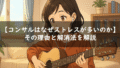
コメント