あー、それってそういうことだったのか!!と長年わからなかったけど、ふとした拍子につっかえが取れるというか、これまでなんでわからなかったんだろうと思うくらいスッとわかった経験ありませんか?
私はあります!!!この記事では、現役ITコンサルの私自身が、「なんかよくパッとわからないなあ」「これって結局どういうこと?」とぼんやりしていたテーマの解像度を上げてくれた本を紹介します。“0→1”の感覚を得られたというか、急に視界が開けたという感覚にしてくれた名著たちです。そういう経験をしたい方にはぜひおすすめです!
本記事では、紹介する本を5冊に絞っています。もし、私と同様にわからないなあと思っていることがあれば、ぜひ読んでみることをお勧めします!
ちなみに、私の習慣を変えてくれた本は以下にまとめていますのでもし興味があれば覗いてみてください。
読書は知識や教養を得る最適な方法
読書は、著者が多くの時間をかけて整理した情報が手軽に吸収できるため、知識を増やすために最も効果的な方法だと思います。読書を通じて新しい知識を得ることはコンサルの仕事の幅が広がることにつながります。読書を習慣化することはビジネス上の観点でも有効なことは間違いないですが、プライベートの観点でも人生を豊かにしてくれるためおすすめです。
解像度が上がったおすすめの本5冊
今回紹介する本は、ITコンサルとは関係ない本も混ざっており、興味関心で読んだ本も含まれて雑多になっていますが、共通点としてはとても読みやすく入門者におすすめということです。そして、何かのスキルを得るにあたって重要な最初の0→1の感覚を得られた本ということです。
まさに私が抱えていた“曖昧な理解”を明確にしてくれた本ばかり。入門者にも最適で、読んだ後に「そういうことか!」と思える本です。
コンサルが「最初の3年間」で学ぶコト
コンサル業界の解像度を上げるには、この1冊。
- コンサルに求められるスキルとは?
- コンサルに求められるメンタリティとは?
といった疑問に具体例を用いながら答えてくれる内容で、特に転職直後の私は、この本を読んで、確かにコンサルってこんな仕事だと、また私がコンサルとして求められていることがふわっとしていた部分の解像度を上げることができました。
世界一楽しい決算書の読み方
決算書とは何ぞやを知りたい方におすすめ。
この本の魅力は、なんといっても、一般的に難しくてとっつきにくい、貸借対照表や損益計算書の理解ができることです。実在する企業のビジネスモデルから、この決算書はどの企業の決算書かをクイズ形式で学ぶことで、決算書の読み方がわかるようになります。流動資産と固定資産って具体的に何?どれくらいの割合だといいの?といった決算書を読み解く力が身につきます。
世界一わかりやすいSAPの教科書
SAPとは何ぞやがわかる初心者におすすめの本。
ITコンサルはSAPの案件に携わることが多く、SAPコンサルでなくても、SAPの全体像や各モジュールがどういった機能なのかを理解する必要があり、この本はとても分かりやすく書かれています。SAP導入のポイントやPJの進め方も書いていて読み手の知りたいことがわかっているなと思いました。
個人的には、ずっともやもやしていたモジュール間の連携(例えば、請求書照合(MM)→買掛金計上(FI)など)がわかりやすく書かれていて、インターネット上にはこれほどわかりやすく書かれている資料がないのでとてもおすすめです。
センスは知識からはじまる
「センス」は才能ではなく、膨大な知識や圧倒的な思考から生まれるものだという視点を教えてくれる本。
- なぜこの色にしたのか?
- なぜこの資料構成にしたのか?
などの問いに対して、「なんとなく」ではなく、論理的に説明できる力こそがセンスであることを教えてくれる本です。その説明をできるようになるためには、知識を蓄える必要があるということでした。確かに、何事もセンスが良いと言われる人は、そういった努力をしているなと思い、自分も気づかされました。センスが良いと言われたい人にはおすすめです。
AWSではじめる新米プログラマのためのクラウド超入門
AWSとは何ぞやを教えてくれる本。ひいてはクラウドとは何ぞやがわかる本。
EC2、S3、RDSなどのAWSの実際のサービスを通じて、クラウドの基本概念と、それがどのようにITビジネスに活用されるかを理解することができます。当初はクラウドって、インターネット上にある何かだと思っていたのですが、各種機能がサービスになっていて、それが各クラウドサービスの中身になっていることを知って、クラウドとは何ぞやがこの本でわかるようになった気がしています。一度読んでみてほしいです。
まとめ
今回は、私が、あー、それってそういうことだったのか!!と理解を変えてくれた本5選を紹介しました。もし気になる領域のものがあればぜひ読んでみてもらえればと思います。
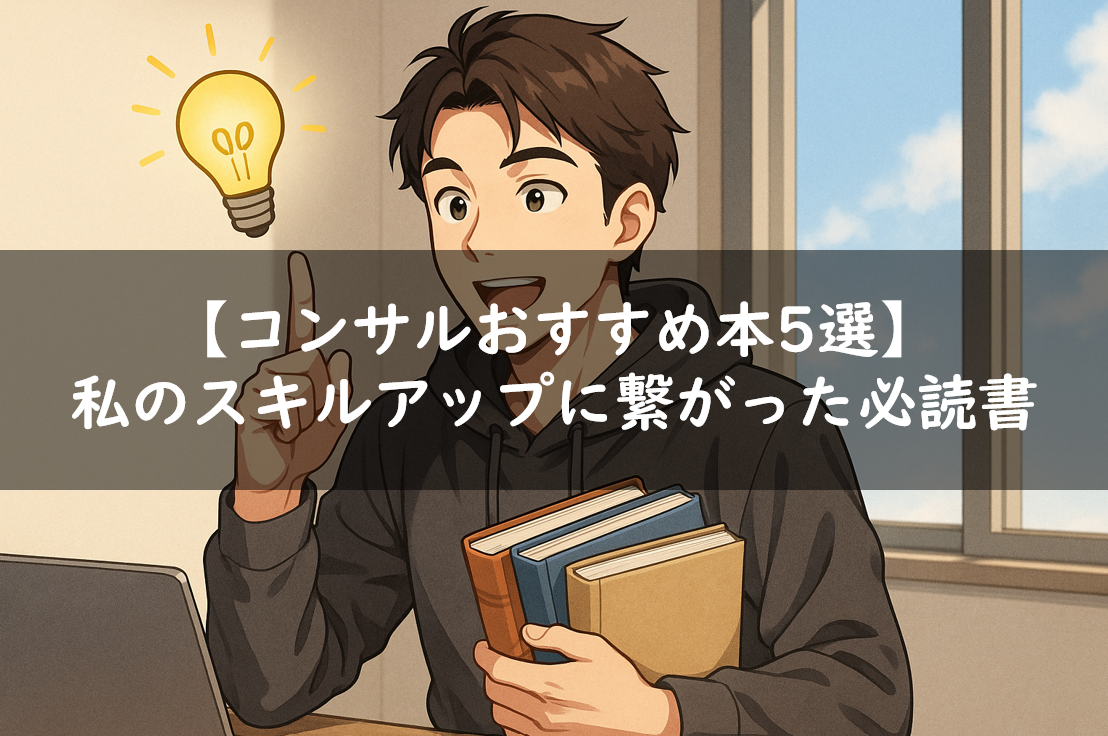
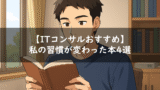
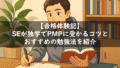
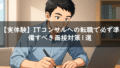
コメント