「SEを辞めたいけど、これって本当に辞める理由になるのかな…?」
「SEって大変な仕事だと感じるけど他の人はどう感じているんだろう」
「SEとしてこのままキャリアを続けてよいのだろうか」
「最近あまり成長できていない気がする」
SEの方であれば、一度はこんなモヤモヤを抱いた人は多いのではないでしょうか。実際、私は、SEとしての仕事にやりがいを感じつつもどこかモヤモヤしていました。
次第にもっと違うキャリアを積んでみたいと思うようになったり、自分が本当にやりたいことはこれなのか、と疑問に感じたりすることが30歳前後で多かった気がします。
SEは様々なプロジェクトを経験できる職業です。しかし、キャリアを進めるにつれて、次第に自分のキャリアパスに関して悩む時期が訪れます。それは「このままジェネラリストとしてマネジメントに進むべきか、それともスペシャリストとして特定の分野で深堀りすべきか」といった悩みです。
この記事では、現役時代にSEを辞めたいと思い実際に転職に踏み切った私が、私の転職理由をお伝えすることで、どういった理由でSEを辞めたくなるのかの参考になればと思います。
SEを辞めたい理由は人それぞれだと思っていて、私は辞めてよかったです。私はITコンサルに転職したのですが、転職してよかったと思う理由を以下に記載しているので、参考になればと思います。
SEからITコンサルに転職してよかった
SEを辞めたいと思う人は多いと思います。IT業界の構造やSEの役割の特性から、辞めたくなると感じるポイントが多いのではないかと考えています。特に同じ役割で比較されやすいITコンサルは、年収が高く、SEより上流からPJを進めることができます。
もちろん大変なこともたくさんあると思いましたが、思い切って転職してみました。結果良かったです。仕事を辞める理由に正解はないと思います。自分が納得するキャリアを歩むのが一番だと思っています。以下では、私自身がSEを辞めたいと思った具体的な理由を紹介します。参考になれば幸いです。
30歳はSE以外のキャリアへの転換点
30歳というのは、ある程度SEの仕事を一人でこなせると感じる頃を指しています。そういったタイミングで、SEを辞めるべきかもしれないともやもやしたことがある方も少なくないと思います。
しかし、実際に辞めるかどうかを決断するのは、簡単ではありません。企業文化や周りの人、仕事内容、いろんなことに慣れてきて居心地がよくなっていると思います。
そういったことを総合して考えて転職するのか、今の会社に留まるのかを考えるべきです。私は一概に転職すべきとも思っておらず、今の会社に留まるメリットもしっかりと考慮すべきだと考えています。そういったことを考えることになるのが30歳で、まさにキャリアの転換点になると思います。
私がSEを辞めた理由5選
結果的に、私はSEを辞めるという選択をしました。
その理由を紹介します。特に1つ目の理由が大きいため、かなり深堀して紹介をしています。SEの方なら同じ悩みを持っていると思います。ただ2つ目~5つ目も少なからず私がSEを辞めたいと思った理由に挙げられるため紹介をしています。
①スペシャリストになるべきと感じた
私は30歳を過ぎたあたりから、常々、ジェネラリストとしてマネジメントを行うだけでは、自分の存在価値があるのか?と疑問を感じていました。SEとして、プロジェクトに関わりながらも、実際には下請けベンダーに多くの仕事を委託し、マネジメントや調整に回ることが多くなります。
こういった役割の中で、技術的なスキルが伸びなく、顧客との本質的な議論の機会が少なく、このままあと30年以上もこの働き方でよいのだろうかと感じるようになったのです。そこで、ITコンサルに転職する道を選びました。
SEの時に主に私が担当していたのは、チームリーダーであったり、PMOといったマネジメント業務でした。チーム全体を管理する役割になることが多く、特定の業務に詳しくなったり、実際にシステムの設定や構築に関わる作業する機会がどんどん減っていきます。
というのも、SEとしてできるけどやらないことが多いためです。自分たちでも要件定義を行い、設計できるプロジェクトもあるのですが、それを下請けベンダーに任せることで利益率を上げるビジネスモデルになっているため、実際に手を動かすことが少なくなります。
このため、SEとしての専門性を深める機会が減り、どんどんジェネラリストとして広い範囲での調整役に徹するようになります。
その結果、SEとしてのスキルはこれ以上伸びていないのではないかと感じるようになりました。提案資料の作成や進捗管理がメインになっていたため、このまま年次を重ねていっても、エンジニアとしての市場価値が高まる実感が持てませんでした。
スペシャリストになれないと感じた具体例
具体的にどういった場面でスペシャリストになれないと感じたかを紹介します。
PM、チームリーダーといった役職が期待される
30歳を迎える頃には、プロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダー、チームリーダーといった役職に任命されることが増えます。
これらには、下請けメンバーの調整やスケジュール管理、顧客とのやり取りが求められますが、実際にシステムに触ったり、資料を作ったりすることは少なくなります。技術的な仕事から、いわゆる管理業務にシフトするため、技術力を伸ばすのが難しくなります。
要件定義等の上流工程でも下請けベンダーが顧客と議論
SE時代は、要件定義や設計などの上流工程からのプロジェクトに参画したとしても、実際に顧客との打ち合わせや業務フローの説明などは、ほとんどが下請けベンダーが実施していました。
というのも、やはり具体的な業務は下請けベンダーの方が詳しいからです。チームリーダーとしてファシリテーションをするだけであり、本質的な議論に関わることが少なくなっていきました。
確かにファシリテーションも重要な役割ですが、それであればITコンサルのような会社の方がスキルが身につくと感じました。実際、同じプロジェクトにコンサルティングファームのメンバも入っていて、その人たちの方がよりマネジメントのスキルに特化していたと感じました。
進捗報告資料がメインになる
要件定義や設計等の本質的な部分を進めるのは下請けベンダーになりますが、顧客への進捗報告はチームリーダーがやらなければなりません。
そのため、表面上の状況を把握できていても、実際に進めていないので、報告者として、実際の進行状況や技術的な理解が欠けたままの報告となり、例えば顧客からの質問が上がったとしても、詳細の説明はチームメンバにお願いしていました。それだとあまり意味がないのではないかと感じる場面が増えていきました。
また、社内管理者向けへのプロジェクト進捗報告も多くなります。そういった社内向け資料の作成も多くなり、本質的なプロジェクト推進に関われる時間も減っていきました。
下請け子会社の見積もりや内部向けPJ損益資料作成に忙殺される
特に下請け会社との調整や見積もり作業、損益管理などがメインになってくる場合があります。
下請けメンバーから見積もりが出されても内容を詳細に理解しているわけではないので、あまり本質的なコメントができないのですが、見積もりをレビューする必要があります。その見積もりになるからと言われるとそれまでなのですが、下請けメンバーとしっかり解像度を上げたうえで見積もりを作成します。
また、内部向けに利益が保てているのか等の報告も多くなり、これらの業務では、実際の技術的な深掘りやシステム設計を行うことは少なくなります。結果として、技術力を向上させるどころか、単なる管理作業に時間を取られてしまい、専門的なスキルを伸ばす機会が減少します。
②大規模プロジェクトほど炎上しがちで心身が疲弊する
私が関わっていたのはSAPをはじめとした基幹システムの大規模プロジェクトでした。SIerとしては売上が大きくなるに連れて、評価も大きくなるのですが、実際のプロジェクトでは、人数が多く、スケジュールもタイトです。調整事項やトラブル対応が山積みで、残業が常態化していました。
特にリリース直前の修羅場は、精神的にも肉体的にも限界を迎えるレベルでした。「大規模案件を回して一人前」みたいな空気感もあり、逃げにくかったです。評価はされるものの、毎回のプロジェクトで消耗していました。
③下請け構造のリスクが大きすぎる
システム開発では、実際に手を動かすのは下請けのエンジニアであるケースが多いです。そして、その品質やスケジュールがプロジェクトの成果に直結します。マネジメントとはいうものの、毎回のPJでメンバが異なるためスキルの判断が難しく、リモートでの管理の難しさによる納期遅延など、リスクが常に身近にある状態で働くプレッシャーが大きかったです。
④年収が役割の難易度に見合っていない
上記にもある通り、多重下請け構造のなかで、顧客とベンダーの間に挟まれ、技術的なスキルが求められることはもちろん、信頼関係の構築等のスキルも求められるとても難易度の高いポジションです。
それにもかかわらず、年収は同じ難易度の業務を行うコンサルタントと比較して1.5倍近くの差がある。責任やプレッシャーは重いのに、それに見合った対価が得られていないのではないかと徐々に感じるようになり、将来的なキャリアを見直すきっかけになりました。
⑤IT自体に苦手意識があった
SEという仕事を選んだものの、そもそも私はITに対して苦手意識がありました。若手のころにあまりコードを書いた経験がなく、プログラミングやネットワーク、データベースの知識もあまりありませんでした。
表面上は仕事をこなせても、「本当にずっとSEでいいのか?」という気持ちは消えませんでした。だからこそ、「ずっとITに関わる職種ではなく、別の領域で働きたい」と自然と思うようになりました。

ITコンサルというキャリア選択
私は、SEとして上記のようなもやもやを抱えながら、2年ほど働いていました。しかし、あるプロジェクトでの経験をきっかけにふと転職してみようと思い立ち、転職エージェントに相談してみました。
SEは引く手あまたで、外資系IT企業、コンサルティングファーム、事業会社のIT企画・・・様々な職種に転職が可能そうでした。その中で私はSEの経験を活かした転職をしたいと考え、ITコンサルに転職しました。とても良い判断だったと考えています。
まとめ:何事でも十分な転職理由になる
私の体験をもとに、SEを辞めた理由を紹介しました。誰もが今感じている不安や違和感も十分な転職理由になります。周囲の目や常識ではなく、自分自身の気持ちを大切にして判断すべきだと考えています。
転職することが正解でも、残ることが正解でもありません。大切なのは、自分の価値観やライフスタイルに合った選択をすることです。この記事が、SEを辞めるべきか続けるべきかで悩んでいる方の判断材料になれば嬉しいです。
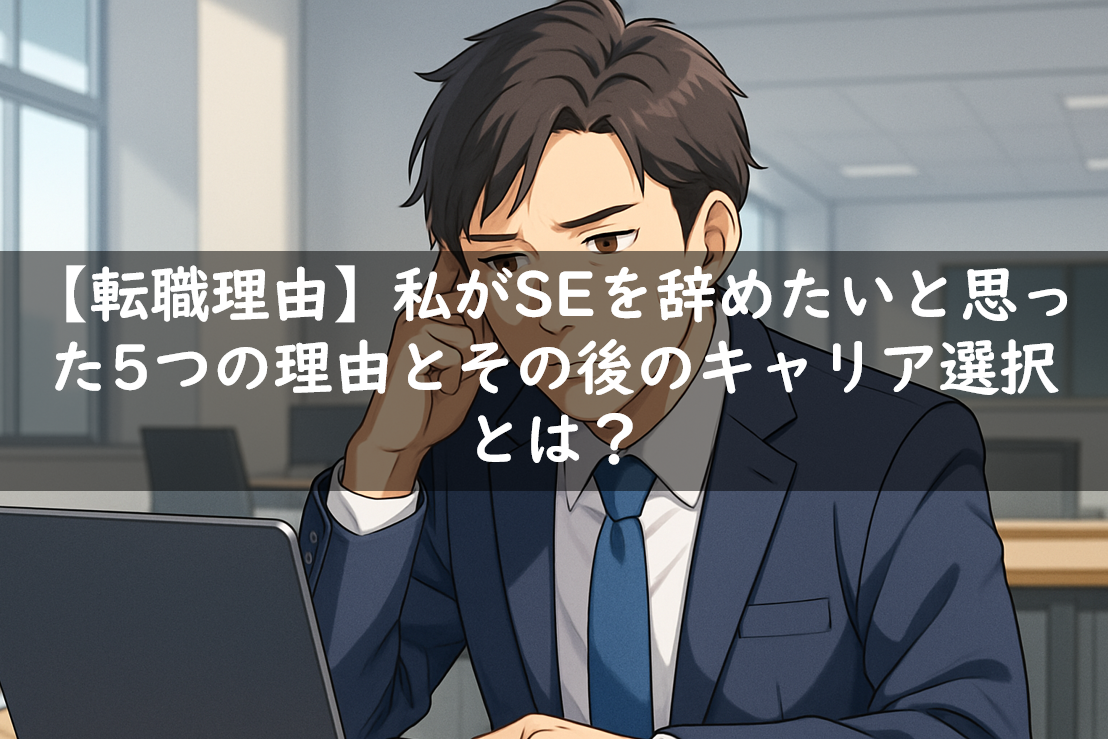
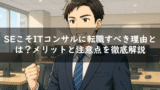
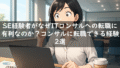
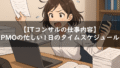
コメント